阿佐ヶ谷どうでしょう。
阿佐ヶ谷のディープな飲み屋~88箇所を巡ります。
番外編「ピノチオ」を探せ! その2



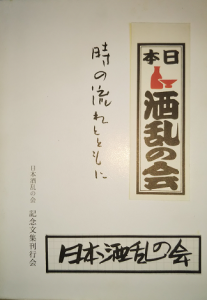
ここまでは資料から分かっていた。そこで本題。ピノチオはいったいどこにあったのだろうか?
支那料理屋ピノチオは阿佐ヶ谷駅北口、いや改札は南口にしかなかったから、踏切りを渡って北側へ出たところの左側、現在はアーケードのある商店街となり、その取っつきあたりにあった(村上護『阿佐ヶ谷文士村』)。
村上はアーケードの「取っつき」と証言している。「取っつき」とは何だろうか?アーケードの東側を南北に走る中杉通りには、現在の杉並区立第一小学校正門前に、当時は小さな吞み屋が立ち並んでいた。これが後に立ち退きになり、現在の都道に拡幅された。
阿佐ヶ谷駅の南口側から踏み切りを望むと、1960年代はこんな風景だった。三菱銀行の位置は変わらない。その先に吞み屋が見えている。この辺りにどんな吞み屋があったのか、再現されるなら覗いてみたいものだ。
 杉並区役所蔵、阿佐ヶ谷名物だった「開かずの踏切」/1962年ごろ
杉並区役所蔵、阿佐ヶ谷名物だった「開かずの踏切」/1962年ごろ
さて私もまとまった時間がとれず、本件は置いておいた。そんなある日、早い時間に『かわ清』で焼酎のお湯割りを飲むことがあり、女将と阿佐ヶ谷の古い街並みについて喋っていた。1960年の一番街について、ずらりと並ぶ店名をすべて書き起こした地図のコピーを手に入れた話など、だったかと思う。
ここで奥にいた高齢の紳士お二人が突然割って入ってきた。「それは私らの仲間が描いたやつでしょう」。
え?描いたと言ったって、もう60年も前の話。私は2018年9月9日に『座高円寺』で山下洋輔トリオの結成時代をテーマに「中央線文化としてのフリージャズ」と題した公演を行い、その関係で一番街の商店会長から入手したのだが。
彼ら、須浪さんと田鹿さんが言う。
「私らは区役所のOBなんですが、現役時代は毎晩のように飲んでいて、『日本酒乱の会』を名乗っておったんです。一番街で何軒もハシゴ酒してね。吞み屋でカネを借りて遊びに行ったりもした」。まあ、おおらかな時代があったものだ。区役所なら給料がしっかりしているとツケがきく。警察や郵便局、消防署も。公務員の給料が飲み代として流通し、阿佐ヶ谷経済を支えた時代があったのだ。
それで私は思い出し、訊ねてみた。「じゃあ、戦前にピノチオがあった場所ってお分かりでしょうか?北口アーケード辺り、私は中杉通りを拡げるのに立ち退きになった辺りの一軒だったんじゃないかとも想像しているんですが」。
答えは興味深いものだった。「カウンターだけの『ぴのちお』なら行ったことがありますよ」。
何?戦後のことだろうから、河北病院近くに移ってからの店のことだろうか?
その辺りは曖昧だったが、「とりあえず『日本酒乱の会』の「先輩」に話を聞いてみましょう」、ということになって、その日は別れた。洋品店「マリヤ」はあの頃からあった、そのアーケード側じゃないか、と須浪・田鹿両氏は言う。そのあたりで次回は集合しましょう、と約束した。
翌週の「ピノチオ」探索の日。「先輩」の三渡さんを含め3人が来て下さった。『日本酒乱の会』絡みの資料やらなんやらを大量に、それと立派な記念文集「時の流れとともに」も持参して。この文集、確かに巻末には「あさがや一番街イラストマップ」が付いている。出回っているコピーの原本はこれだったのだ。それに「日本酒乱の会」の短冊風シールも。会合の日はこれを会場に貼ったらしい。飲むことに込める気合いが桁違いだ。
見せられたのが昭和43(1968)年の地図。これは凄い。三菱銀行の前からまっすぐに線を引くと現在の中杉通りの東側ラインになるから、その上に南北に並ぶ一列の店と、細い細い旧中杉通りを挟み、西に南北一列の店の「東側半分」が立ち退きになり、中杉通りが現在の幅へ拡張されたのが分かる。

私はと言うと、こんな証言を見つけていた。
ピノチオの店は左隣の時計屋が権利を買つて、次に土地の金持ちで岡さんという人が買ひ、岡さんの倅のシゲルさんといふのが経営した(井伏鱒二「阿佐ヶ谷将棋会」『荻窪風土記』井伏鱒二全集第27巻、筑摩書房、1999)。
「左隣の時計屋」とは昭和15年に佐藤清からピノチオを譲渡された加藤という大学教授の家のことだろう。では時計屋はどこにあるのか?あったあった。アーケード内、マリヤの筋向かいで地図上に「松井時計店」とある。その右隣がピノチオのあった場所とすれば、「栄ヤ傘店」とある。
時計屋は現在のどの店なのだろうか。「そりゃ渡辺金物の奥さんに聞かなきゃ」と「日本酒乱の会」のみなさん。私も含め4人で混雑する渡辺金物店にどやどやと入店。で奥さんに訊ねると、あっさりと答えが返ってきた。「いまのネパール料理屋さんが時計屋さんだったわよ」。

ということで、「ピノチオ」はネパール料理屋の右隣、「元祖 肉汁餃子のダンタダン」ということになる。発見を祝して記念撮影をパチリ。ピノチオの焼売はたいそう旨かったそうだから、焼売から餃子という繋がりも流れを感じる。
このあと一杯やりながら話を伺うと、三渡先輩は阿佐ヶ谷図書館の担当をしておられて「阿佐ヶ谷文士村」の命名に尽力、その節は許可をいただこうと井伏邸に何度も足を運んだという。井伏の謦咳に触れた方であったのだ。
他のお二人はというと――、土木関係で、阿佐ヶ谷の暗渠化に尽力されたという。そして須浪さんから衝撃的な推測が飛び出した。
「井伏先生宅から阿佐ヶ谷駅まで歩くのに、井伏先生が中杉通り近くまで二高通りを歩くなんてありえないです。先生の散歩の趣味からしても、まず二高通りは歩かず、通い慣れた荻窪駅に向かうはず。途中に井伏が亡くなることになる衛生病院がありますから、そこから東、阿佐ヶ谷に向かうには旧道が2本あります。松山通りに出るとしたら墓地脇の道、もう一本は直接なか卯に出る道です」。

これはまったく推測でしかないが、衛生病院から東へ向かうと、ちょうど日大二高から南下してくる道とぶつかる。そこでどの道を選ぶかだ。日大幼稚園がある通り、「杉並区知る区ロード」の暗渠通り、その南が墓地脇へ向かう道、なか卯に出る道と4つの選択肢があり、そのうち井伏が選ぶであろう旧道は2本だという。1本はすぐピノチオに出る。しかしもう1本は河盛好蔵の家近くを通って墓地脇へ。それはなんと青二才前で松山通りに出るのだ。そうだとすると、いやそうであって欲しいが、なんと井伏鱒二は墓地の角で青二才の土地を眺めつつ右折して、ピノチオに向かったことになるのだ。

と書いて私はこの物語を終わろうとしていた。ところが私はネットで驚くべき発見をした。とあるシンポジウムで杉並区の屋敷林につき報告した御仁がおり、その人物はぴのちおの所在地についてアーケード駅側入口から西友の間と指摘したという。その御仁は松原、つまり私であった。
私は村上護の『阿佐ヶ谷文士村』(春陽堂書店、1993)を読み、「現在はアーケードのある商店街となり、その取っつきあたりにあった」という表現を、「曖昧な表現をするものだ」と訝しがりつつもシンポジウム時には受け入れていたのだ。
ところが今回、井伏鱒二「阿佐ヶ谷将棋会」の「ピノチオの店は左隣の時計屋が権利を買つて、・・」という証言を見つけ、(昭和43年のではあるが)「日本酒乱の会」からいただいた地図に照らし合わせ、アーケード内の「松井時計」隣を本命視するようになったのだ。
けれども私とは独立に、岡崎武志が「アーケード駅側入口と西友との間」説を採っている(「阿佐ヶ谷・荻窪文学散歩」青柳・川本、同)。2つの説を比較せねばなるまい。
岡崎の論拠は以前の私と同じ村上護だが、引用する文が奇妙である。「・・現在はアーケードのある商店街となり、その取っつきあたり、新光堂という用品店の場所にあった」。前半はまったく同じ文章に、なぜか「新光堂」うんぬんが付け加わっているのだ。引用元は『文壇資料 阿佐谷界隈』。この本は講談社から1977年に出版されている。

「酒乱の会」持参の昭和43年地図を拡大してみると、確かにアーケード入り口に「新光堂洋装」とある。しかもアーケード内から見れば、その3軒隣に「鹿島時計店」というのがあるではないか!
慌てて杉並区中央図書館へチャリを走らせ、収蔵されている『文壇資料 阿佐谷界隈』を借り出す。確かにこちらの文章には「新光堂うんぬん」と書かれている。
こんなことだろうか。村上護は1977年には講談社から『文壇資料 阿佐谷界隈』を出版した。この本には中杉通り側から撮影した新光堂の写真も掲載されている。
そして1977年、世尊院が真っ二つになったとの記録が世尊院に残っているのでその年に、新光堂を含む店の南北の並びは、東側半分が立ち退きになり、取り壊された。現在の歩道と中杉通り西側ラインである。
確認すべく、私は今川の杉並区法務局へ出向き、土地台帳を閲覧した。昭和12年だと建物の所有者名はもう分からなくなっている。そこで「ダンダダン餃子」と「新光堂」に相当する土地の所有者名を見てみた。残念ながら双方とも「佐藤」という名前ではない。ぴのちおを譲渡したというのは、上物だけ売買したのだろう。
さらに地割りを示すブループリントでも、アーケードと中杉通りの間は、南北に東半分の店舗並びが切り取られて売却されている。現在、中杉通り側には店は開かれていない。

そこでアーケード側に回ると、その位置に「CREA」なる文字のウィンドウがあった。素敵に着こなすご婦人向けのブティックだ。その「CREA」の下の文字を見ると、私の目は釘付けになった。なんと小さく「SHINKODO」と書いてあるではないか。驚いたことに新光堂はアーケード側で継続していたのだ。
奇々怪々な話ではある。村上はネタ元を書いていないが、「ぴのちお」は新光堂の場所にあったという話は誰かから聞いたのだろう。村上は昭和13年生まれだから、戦前期のピノチオを記憶していた可能性は低い。
そして1977年。地図からも分かるように、アーケード東側に当たる多くの店は、アーケード内と中杉通り側で背中合わせになっていた。ところが新光堂は大きく、双方を兼ねた面積があり、中杉通り側の半分だけ取り壊された。
さらに1990年代になって阿佐ヶ谷図書館が創設される。その際、区役所の三渡先輩が井伏宅に日参、甲斐あって「阿佐ヶ谷文士村」という言葉が成立した。併せて村上が1993年に『阿佐ヶ谷文士村』を春陽堂書店から出版する運びとなったが、実質的にそれは『文壇資料 阿佐谷界隈』の復刊であった。その際、村上は路面店であった新光堂は閉店したと思い込み、「新光堂うんぬん」の部分を削除した――。
村上は正面玄関をえぐられた新光堂は店全体が消滅したと考え、文章を削除したのだ。岡崎武志も同じ文章で「すでに現在、その新光堂はない」と勘違いを受け継いでいる。
だからいったん断定しておこう。ここが「ピノチオ」があった場所だ。井伏は(30年前からあったとして)鹿島時計店を「左隣の時計屋」と書いているから、アーケードの内側、現在のこのCREA入り口をピノチオの入り口として眺めていたことになる。
想像していただきたい。CREAの入り口から硝子の中を覗くと、薄暗い店内に天井から大提灯と巨大魚の鰭がぶら下がり、井伏が座りビールを飲んでいる。昭和10年に「『サヨナラ』ダケガ人生ダ」と訳し、12年に『ジョン万次郎漂流記』で直木賞授賞と仕事は順風満帆。しかし翌13年に店内で女将さんにお嬢さんにどうかと太宰を紹介し、断られた。その結果、次の縁談で太宰は再婚し、荻窪を離れ三鷹へと転居していく。『斜陽』『人間失格』と矢継ぎ早にヒット作を世に問い、昭和23年に入水自殺を敢行する。
そんな訳で、村上護に振り回されて餃子屋前の「日本酒乱の会」との記念写真は無効になってしまった。しかし本件の顛末を確認すべく須浪さん宅を訪れると、井伏鱒二全集2セットを披露しつつ、こんな話を聞かせて下さった。井伏の「「サヨナラ」ダケガ人生ダ」は、自分たちの愛唱する詩である、「酒乱」会員は、いつも一番街で他の訳詩とともに吟じていたのだ、と。
井伏の言霊は、1960年代からは一番街に、2016年には青二才に降臨していたのだ。
コノサカヅキヲ受ケテクレ
ドウゾナミナミツガシテオクレ
ハナニアラシノタトエモアルゾ
「サヨナラ」ダケガ人生ダ
と今を生きる阿佐ヶ谷の酒飲みたちに知らしめるために――。

最近のエントリー
- 和メリカン
- ふぐ ちゃんこ料理 たなか(閉店)
- 番外編「ピノチオ」を探せ! その2
- 番外編「ピノチオ」を探せ! その1
- 酒女 うろこ(閉店)
- BAR頻伽(びんが)
- 煮込みBAR ゴールデンスランバー
- ROCK BAR EDGE
- Elisa(エリーザ)
- 春日
- 狂った阿佐谷の夜 BAR Lunatic Asylum(再開)
- 俺ん家(閉店)
- よるもすのたり(閉店)
- 夜カフェ ポポット(おでんbar「もみぢ」として新装)
- 越川
- 山路(店主・よし子が亡くなりました)
- コタンの笛
- Arrow
- Bar Rock India
- えいかつ
- ユープケッチャ
- やんたけ(閉店)
- Bar Brock
- ヨシロン
- 青二才(移動)
- bar 暁
- BAR 蛍(閉店)
- イザラ Les cuisines et Les boissons
- ラ・メゾン・クルティーヌ
- 葉山房
- Beauty salon & bar「Caffeine trick」(閉店)
- Cave(閉店しました)
- 角打ち処「裏の部屋」
- 道心
- 薫屋
- 黒猫茶房
- KATATSUMURI BAR(閉店)
- 大衆割烹 和田屋
- Rock kitchen 1984
- ガンバラネBAR
- か〇〇(週一開店、いつかは未定)
- はる(閉店)
- ありがた屋 とりい
- うまい魚 たつや(閉店しました)
- カフェ 〇○〇〇ー/カフェ 珈司(阿佐ヶ谷南1-36-19あゆみ荘に移転)
- ギャラリー・スナック ぱすてる屋(閉店、静岡市清水区江尻町8-27で営業)
- food and drink とらや
- Bar Vesper(移転→中杉通り元プラモデル屋→2021夏閉店。店主がお亡くなりになりました)
- 居酒屋 丸山
- 餃子坊 豚八戒
- ひなた珈琲/パンドラ
- ビストロ 猫の髭(閉店)
- Beer Bar STONE
- 阿佐ヶ谷 バードランド
- 割烹互閃 ~GOSEN~(閉店)
- 月は夜を見て(閉店)
- 十六夜(いざよい)(閉店)
- あそこ(ナント、閉店。残念です)
- 司 tsukasa(ママが亡くなりました。閉店)
- Stardust (閉店)
- Tarot bar アーサ(閉店)
- bar Night Train
- Rudie ルーディー (閉店です。阿佐ヶ谷の音楽はどうなるんだろう…)
- スナックバー 舞子(閉店)
- みちのく(閉店)
- カレーバー Orphee (閉店)
- うずまき(閉店したようです。残念)
- 馳走 HI FU MI(一二三)(閉店)
- 木の蔵
- Chicago
- Tabasa
- Cotton Wagon(閉店)